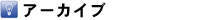
チャグチャランPRT日本文民事務所から届いた過去のエッセイを紹介します。
「独立人権委員会会合」
独立人権委員会の会合で話し合われたこと、それは2人の少女についてである。ゴール県の北にあるガルミン地区で夫が妻をカラシニコフで撃ち殺すという事件が起こった。事件はそこから始まるのである。それを知った妻の家族たちは、村の長老たちに仲介をしてもらい夫の家族より“血の代償”を払ってもらうことで納得した。その“血の代償”に払われるもの、それは2人の少女である。2人の少女は妻の家族のメンバーの許婚として差し出された。因みに、その少女の一人は2歳半である。少女ともいえない赤ん坊である。しかも“血の代償”として支払われた少女たちは夫の家族の中から差し出されたものではなく、彼の貧しい親戚の中から差し出されたようである。その夫は、のうのうと今もその村で暮らしている。会合に出席していたアフガン警察署長は言う。“彼らは自分たちで問題を解決した。政府の介入を望んでいない。”鼻からこの事件に深く介入する気はないようだ。最終的に独立人権委員会の名前で県知事に殺人事件の捜査依頼と2人の少女をそれぞれの家族の元に返すための手続きを依頼することになった。この話をリトアニアの開発アドバイザーと目を見開きながら聞く。いったい私たちはいつの時代にタイム・スリップしてしまったのだろう。どうすれば、私たちは現代に戻れるのだろう?出口のない迷路に迷い込んだような気分になる。(石崎)
「リトアニアの国旗交換式」
PRT基地内の広場でリトアニアの国旗交換式が執り行われた。旗手の後ろにリトアニア軍部隊が整列している。参謀長が報告を受けた後、司令官が登壇すると、4人の兵士が新しい国旗とともに、PRT参加国の旗を揚げる掲揚台の前まで行進して来た。ポールの傍に控えていた2人が今まで使用した旗を降ろし、丁寧に折りたたむ。1人が古い旗を捧げ持つ間、もう1人が国歌演奏に合わせて、新しい旗をゆっくりと掲げた。全員の動作に国旗(=祖国)を大切にする気持ちが表われている。リトアニアの黄・緑・赤の三色旗は、実り豊かな大地(黄)、国民の活力と自然(緑)、自由を守るために流された血の色(赤)を表すとされている。この三色旗は1919年1月1日に国旗に制定されたが、5日後にロシア軍がリトアニアの首都を制圧した際に、旗から黄と緑の色が抜かれ、ソ連の赤旗が残された。三色旗は、翌1920年8月にリトアニア軍が首都を奪還した際に戻されたが、同年10月にポーランドが首都ヴィリニュスを占領したことにより、再びその姿を消した。独立の気運の高まりとともに蘇り、1989年に再び国旗として制定された、自由への闘争を象徴する旗なのである。(今井)
「ゴール県での連絡手段」
チャグチャラン市内の政府関係者であればいつでも会えるが、地方の有力者に連絡するときはいつも苦労する。先方は、電話を持っていない。電子メールももっていない。そもそもコンピューターを有していない。従って、レターを書くことになるが、そのレターの届け方が実に原始的である。郵便局はあるものその機能は果たしていない。住民も郵便局を利用することはなく、近いうちにその場所に行く人をみつけて、その人に託すという手段に頼っている。現在、アフガン暦では1388年。時々、西暦1388年以前の時代にタイムスリップしたような感覚に陥る。(官澤)
「ゴール県刑務所訪問」
ゴール県の刑務所を訪問した。目的は、同刑務所の唯一の女性受刑者に対する健康診断である。PRTにはリトアニア人女性医師はいるものの、アフガン人女性通訳は、住民が良からぬ誤解をしないように雇っていない。その為、急遽女性医師の通訳として同行することになった。アンドリュース政務アドバイザー、女性医師他と共に刑務所に向かう。刑務所関係者と面談をし、女性医師と私の2名が、刑務所向かい側にある土塀に囲まれた一軒の家へ。そこに現在女性受刑者が収容されている。門扉前で警備している男性刑務官の横を通り過ぎ、何故か、内側からロックされた門扉の中へ。中には、女性刑務官一人と1-2歳の子どもが二人(そのうちの一人は女性受刑者の子どもである)。女性受刑者が我々に同行してきた男性の刑務官に腕を引かれ、部屋に入ってきた。彼女は当県の南部に位置するパサバンド郡出身で夫からの暴力に耐えかねず、夫を殺した殺人罪で16年間の刑に服役中である。よく彼女は夫の家族に殺されずに生き延びられたなというのが私の一番の感想である。しかし、男性刑務官に腕を引かれた彼女を見て驚いた。その理由は、当地では、男性が家族・親戚以外の女性に触れることはまず有り得ないからである。男性刑務官が、囚人とはいえ、女性に躊躇無く触れることは当地の文化ではまず考えられず奇妙である。16年間の刑期中に、虐待があるとしたら正に地獄である。また、服役後も夫を殺した彼女に故郷での居場所はないであろう。こういう事案に触れるにつけ、開発に携わる者として無力感に襲われる。伝統的、且つ保守的な家父長制の下で、女性の自由が極めて制限されている当地に生まれなかった自分の幸運を思わずにはいられない。(石崎)
「ラル・サンジャンガル郡出張」
チャグチャラン市内より更に1,000メートル近く標高の高い。ラル・サンジャンガル郡は、チャグチャラン市内に比べ気温も6度近く下がる。氷点下の中の2泊3日の出張だ。安全のため、民宿などの建物の中には泊まらず、外に組み立て式簡易ベッドに寝袋で寝ることとなる。毎日10時間以上車で揺られながら、あちこちを移動する。まさに体力勝負だ。星空図鑑を同僚から拝借し、夜は星座観察をする。上着4枚、マフラー、帽子フル装備で寝袋に包まって寝るものの、夜中寒さで2、3度起きる。外気に触れている顔が寒く、寝袋に顔を突っ込むと寝袋と体にあいた隙間より外気が流れ込み全身が冷たくなる。次に目覚めるときは朝であるよう祈りながらまた眠りにつく。朝、目が覚め、ウェット・ティッシュで顔を拭くと、顔は砂だらけである。
出張中一番困ることはトイレである。果てしなく続くゴール県の土漠は、緑が少ない。休憩中一緒の車に乗っている面倒見のよいCIMIC(民軍協力部門)のアンドリュースは“ここは駄目だ”とぼそっと呟く。何のことかわからず、ぼんやりしていると“ここからあと2時間は休憩がない。どこかに行った方がいい。”といってくる。一人でトコトコと皆の輪を離れるわけには行かず、私のトイレ探しの旅には必ず銃を持った兵士が同行する。そんなわけで落ち着かない野外のトイレは3日目の私に腹痛をもたらす。あと目的地まで何時間かかるのかわからない中、腹痛をアンドリュースに伝える。すると彼は無線を通じリトアニア語で全車両に私のトイレ探しを指示。“あそこの藪はどうだ?”という彼の言葉を無視し、民家に駆け込み難を逃れる。もちろん民家に駆け込む私の後ろを銃を構えた兵士が追ってくる。PRT基地に無事帰還し今まではトイレやシャワーが外にあり、寒いし面倒くさいなどと文句を言っていた私であるが、一人で基地内を歩き回る自由を今噛み締めている。(石崎)
「ゴール県開発会議」
ゴール県開発会議。県内10郡の要望を取り入れた開発計画を中央政府に提出するべく、ムニブ知事をはじめ県政府関係者が奮闘している。計画作成を通じ、少しでも県民の生活向上を実現させよう、という熱気が我々にも伝わってくる。どの開発事業に優先順位を置くかという議論においては、多様な社会グループに属する各人の関心は、自己のグループにどれだけ有利かという点に集中する。最終的にグループ間の調整がつかず、「これも欲しい。あれも欲しい」といった総花的な議論にならないようにするには、知事の指導力が問われることとなる。
行政能力が脆弱で、伝統的な部族社会が根強く残るゴール県では、中・長期的な公共の利益という視点から開発を考えることはとても難しい。どうしても自分の所属する部族がどれだけ裨益するかが重要となる。まずはゴール県民の意見に耳を傾けながら、県民全体の利益と伝統的グループの利益のバランスをとりつつ開発を進めていくという高度な判断が要求される。(今井) 「草の根無償支援署名式とマデラサ村視察」
知事公舎で日本の草の根無償支援4案件の署名式が、ムニブ知事、県政府、PRT、当地に事務所を置く国際機関及びNGO等の代表約100名の出席を得て盛大且つ厳粛に実施された。県知事やNGO側からのお礼の挨拶、その熱のこもった雰囲気に日本に対するゴール県の期待の高さが感じられた。署名式の後、今回署名した4件の一つであるマデラサ女子小・中学校建設予定地(現在は「青空学級」で校舎なし)視察のため、約25kmの道を約1時間15分かけて移動した。青空学級ということでもあり、単なる山間の空き地を視察するだけのことと思っていたら、建設予定地の直前から500名以上の村人達が、長老グループ、女性グループ、子供のグループが男子と女子に整然と別れ、道なりに数百mにわたる花道を作って歓迎してくれた。女子生徒からは花束の贈呈を受け、建設予定地に礎石をおく式典まで容易されていた。ハリルード川のほとりの木陰に絨毯を引いてしつらえられた場所での長老等の挨拶、女子生徒による歌、最後は、村で一番立派な家で、座布団のように大きな丸いナン、ヨーグルト、羊の煮込みといったメニューによる昼食のもてなしを受けた。署名式は、マデラサ女子小・中学校建設計画の最初の一歩にすぎない。先ず事業計画に沿って校舎建設を行い、完成した校舎で女生徒が喜んで勉強できるようになるまで、十分にモニタリング、フォローアップしていくのがPRT事務所の大事な務めとなる。(折笠)
「ゴール県の孤児院」
今日はゴール県唯一の孤児院を訪れた。現在リトアニアがその孤児院建物の新規建設を予定している。親を亡くした子供たちもいれば、経済的理由から同施設に預けられた子供もおり、現在は男子144名と女子6名がいる(女子は近くの親戚の家に預けられ、食べ物の提供を受けるのみである)。男子の孤児の割合に対して、女子の孤児が非常に少ない。同施設に入ると、小・中学校教育を受けることが出来るため、男子を優先して家族や親戚が送り込む、貧しい家庭の女子は強制結婚等で経済的余裕のある家庭にもらわれていくという事情があるとよく聞くが、労働社会福祉局や孤児院の担当者は、はっきりと答えない。県当局者との関係構築も大切であるが、それ以外の情報源を持つことも大切である。(石崎)
「シャフラック郡出張」
ゴール県西部に位置するシャフラック郡に出張した。朝3時に出発し、ジャムラ・アライン・メダン村に午前10時に到着した。村人には訪問時期は安全上の理由で知らされていないが、広場に10台の車両が到着する頃には200人を超える村人が集まってきて(女の子供数人以外は全て男性)大騒ぎとなった。真っ先にPRT司令官が通訳を連れ、人ごみに分け入って村長に挨拶し医療部隊の3名の医者が同行している旨伝え、診療場所の提供を依頼した。司令官と村長のトップ会談を全員がじっと声も出さず見守っていたが、村長の采配で場所が決まると、男性用、女性用それに歯科用の3箇所に別れ診察が直ぐに始まった。司令官、政治顧問、ウクライナ人軍事顧問、CIMIC(軍民協力)担当他数名は、村長及び約15名の村の代表による歓迎のお茶会に出席した(お茶菓子はイラン製のキャラメル)。約30畳の広さのUNICEFテントで靴を脱ぎ胡坐をかいて車座で歓談する姿は日本の田舎の寄り合いを思い出させる。司令官同行者、医療部隊、見張り役以外の軍人は、ダリー語の新聞、ダリー語版リトアニア童話、ノート等を配ったりサッカーボール、バレーボールで子供達と遊んだりしていた。いつもPRTのジムで見かけるペンシルバニア州出身米兵はフリスビーを教えていた。マルチ・エスニック、マルチ・カルチャーの何とも不思議な空間がつくり出されることとなった。(折笠)
「軍民協力とは?」
PRTは軍民協力の場であり、軍関係者(治安維持)と文民(復興支援)間の緊密な調整の上に立った活動がいろいろな形で実を結んでいる。独立のCIMIC(民軍協力)部隊が我々文民の活動を支援したり、MLOT(軍事パトロール・チーム)がパトロールの際に、日本の支援で建てた学校の状況を撮影してきてくれたり、我々文民がローカルNGOから聞いた情報がシェアされるなど、日々密接な協力関係にある。
治安と復興を車の両輪として包括的なアプローチをとることが今のアフガニスタンでは必要不可欠であり、民生支援活動を治安が安定しない地域でもアフガニスタン国民に提供するためにはPRTは重要な役割を果たしている。(官澤)
「緩やかな男女隔離」
ここチャグチャランはタジク系のアフガン人が多く居住している。一般的にタジク系は他民族に比べ、公的・私的空間での男女隔離が緩やかだといわれている。当地では、市内の女性は頭からすっぽり被って顔も体も隠れるブルカではなく、体の線は隠れるが顔は見えるチャドール又は、長めのコートとスカーフという姿が多い。又、女性一人で外を歩いている姿も見かける。首都カブールに比較すると他地域からの人口流入が少ない分、女性が比較的安心して外に出られる環境が整っているようだ。(石崎)
「忘れ去られた県」
チャグチャランのあるゴール県は、ムニブ県知事によればアフガニスタン全34県のうち2番目に貧しい県とのことである。高い山々に囲まれ、交通インフラが整備されていないので、なかなか経済は発展しない。我々はまだ体験していないが、冬の半年間は積雪のため交通・流通機能はほぼストップするという。
舗装道路もなく、地元の人々はよく「忘れ去られた県」と自嘲するが、それだけに日本文民がこの県にきたことにいつも感謝される。ここの人は誰でも、日本がやってきたことを知っていて、期待も大きい。それだけに我々の責任も重い。(官澤)
|

