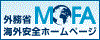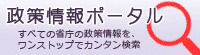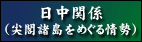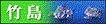|
Mr. Iwaz Ali |
私が13歳のとき、当時カブールに住んでいた日本人の家で掃除夫として5年間働いたのが、日本との最初の出会いです。そこで日本語を学び、以後約40年間、アフガニスタンで働く日本人と一緒に働いてきました。
途中ソ連がアフガニスタンに侵攻し、アフガニスタン在住の日本人の多くが帰国しました。私自身も難民としてパキスタンで約20年間靴職人として働きました。しかし、日本人の勤勉さ、優しさに触れながら育ったので、祖国に戻り再び日本人と一緒に働くことは私の夢でもありました。
2001年タリバーン政権崩壊後、家族と共にカブールに戻ってきました。私はすぐに再開された日本大使館に赴き、警備員として働くことになりました。それから約10年、私はすでに一線を退きましたが、今も大使館の人々の買い物等生活のサポートをしています。現在のアフガニスタンは治安が非常に悪く、ここで働く日本人の人が自由に町で買い物をすることはできません。私自身も偶然買い物に出かけたショッピング・センターで自爆テロがあり、危うく巻き込まれるところでした。このような日常的に危険をはらむような場所で、長きに亘って日本のアフガン支援を側面支援できることを誇りに思います。
またこれまで一緒に働いた日本人の同僚の招待で、2009年に7日間日本の地を踏むことが出来ました。東京と京都を昔の同僚たちと一緒に巡りました。発展して綺麗な町並みを見る度に、祖国アフガニスタンの不安定な治安と開発途上の町並みを思い出さずにはいられませんでした。アフガニスタンに帰国し、アフガニスタン復興のために尽力をつくしてくれる日本人の仲間をこれからもサポートしていきたいと思っています。
「日本での思い出とアフガニスタン」
 |
Mr.Jahid Zabuli |
2004年から2009年までの5年間、岐阜大学連合獣医学研究科に在籍しました。日本滞在中は、学会の発表や研究のために北海道や岩手など日本各地を飛び回り、とても忙しい日々を過ごしました。
日本に来た当初、生魚(刺身)を食べる日本人に驚いたり、わさびを野菜の一種と勘違いし、一塊バクッと口に入れ号泣したり、裸でグループで野外で入るお風呂(温泉のこと)に最初誘われたときは恥ずかしさでどうしようかと思った。
そんな驚きの連続だった日本の生活にも慣れ、今は日本のお寿司、ワサビ、そして温泉がとても懐かしい。
現在はカブール大学獣医学部で他のアフガニスタン人帰国留学生と共に、日本で学んだことをアフガニスタンの発展に生かすには何をすべきなのか日々模索しています。学生への指導だけでなく、アフガニスタンにおける畜産業再生のために日本の経験を生かしたいと最新の人工授精技術等の研究をしています。
「教師として生きる」
 |
Ms. Raihana Royan Rahimi |
タリバーン政権下、女性の私は教鞭をとることが許されていませんでした。それどころか、女性としての自由が奪われていくアフガニスタンからパキスタンへ2年間の難民生活を余儀なくされました。
そのような不自由な生活から一転し、日本での5年間に亘る留学生活は、言葉の壁という問題にぶち当たりながらも、安心して家族で過ごせるという喜びと、何よりも友人と共に学べる喜びに満ち溢れたものでした。
私の専門は微生物学です。タリバーン時代は大学での実験は許されていませんでした。今でも機材が満足に揃っていないため実験をする機会は限られています。日本に留学中、大学は実験をする機会を私に度々与えてくれました。実験をすることは、その裏にある倫理などを明確に理解することが可能となり、実験の重要性を再認識することとなりました。日本の技術は非常に高く、それをアフガニスタンの現在の技術レベルに置き換えて教えることは非常に難しいです。しかし教師として学生に実験をする機会を与えること、新しい
技術に触れさせること、それをアフガニスタンで行っていけたらと思っています。
「アフガニスタンと日本の橋渡し」
 |
Mr. Mohammad Karim Haidar |
京都大学大学院で薬学を専攻しました。同じクラスには30名以上の学生が在籍し、その内3分の1はタイ、中国、ベトナムからの学生でした。国際的な研究環境下で、また真夜中でも必ず誰かが実験をしているという熱心な研究者たちと共に学べたことは、私の財産です。
カブールに戻り一年、現在は大学で薬学の指導をしています。帰国当初は、日本とアフガニスタンの研究環境の違いに非常に落胆しました。今では、日本で出来たような実験が全く行うことができません。しかし我々アフガン人研究者にとって重要なことは、アフガニスタンの将来のために学術分野で日本を初めとする諸外国と連携し、未来の研究者のための環境を整えていくことです。私は日本の大学院を修了したものとして、日本の大学と連携し、研究環境を整え、アフガニスタンの将来のために貢献したいと思っています。